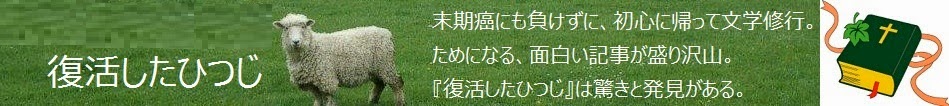|
| 拡大 |
2014年2月28日金曜日
2014年2月27日木曜日
2014年2月26日水曜日
2014年2月25日火曜日
2014年2月24日月曜日
2014年2月21日金曜日
2014年2月20日木曜日
夏目漱石(今から十年前)
今回は僭越かと思いながらも、少しばかり託(かこ)つかせていただくことにした。従って読者の皆様方には、何卒、曲解のないようにお願い申し上げたい。
購読の契約をした覚えが全くないのに、数ヶ月前から、或る(キリスト教)教団が発行している雑誌が日本から送られてくる。その項目の中に、夏目漱石のことについて書かれている記事が掲載されていたので、たちまち私の興味を惹いた。
だが、その内容が余りにも独断と偏見に陥っていたので、私は非常に驚該してしまった。執筆者は七十代の牧師であり、また、キリスト教の要職にある人物であった。それ故に、購読者はエッセイの誤謬を鵜呑みにしてしまう危険性がある。
従ってこの種のエッセイは、個人誌か同人雑誌に発表されることをお勧めしたい。考えようによっては、受け売りや知ったかぶりよりも悪性であると思う。なぜならば読者に謬見を与えるからである。
まず、このエッセイの中で、夏目漱石は自殺しなかったので、漱石は自己のエゴイズムと闘わなかったと断言している。おまけに、漱石は発狂もしなかったと述べている。更に、漱石は極悪人であると嘲弄するくだりには、閉口してしまった。
夏目漱石論をここに書き始めると、枚挙に遑(いとま)がない。また、論文的考察は本欄に書くべき属性ではないので、大きく割愛させていただくが、単刀直入に弁明すると、この度の夏目漱石のエッセイを書いた聖職者にとって、漱石の思想やら創作の構想が十分に首肯(しゅこう)しがたかったのではあるまいか、と帰趣するに至った。
漱石のように、『自己本位』(自己のエゴイズム)と真剣に向かい合って闘った作家は数少ないのである。
漱石には五十年の生涯において、少なくとも三回、大きな精神異常の時期があった。文献によると、漱石は東京大学の呉 秀三教授の診察を受けて、追跡狂と診断されている。これは精神分裂病の一種である。その他の専門医の論文をひもとくと、躁鬱病であるとの意見に分かれている。
また漱石は『則天去私』の世界をめざして、狂気と真っ向から対峙していたのである。
私はここに、錯誤を犯している箇所を順番に上げ連ねて、訂正していくつもりはない。また、それをやるときりがない。ただ、一生懸命な姿勢の裏付けであろうが、件の漱石のことに付いて書いた作者は、自分の造詣が深いものを自己のスキルの一つとして思い込み、伝道への手段として活用しながらも、独善的になってしまっていることが極めて遺憾である。
けれども、それが、その者にとって真のエキスパート(賜物)であるならば、共に祈る必要性がある。だが、実体のない理論は、残念ながらディレッタントであると言わざるを得ない。即ち、スペシャリストではないのに、講壇に立つ際や、活字媒体から原稿を依頼されると、そのことに付いて、自分が専門家になったような錯覚に陥ってしまう。
随分と生意気なことを言うようで、お叱りを被るかも知れないが、著名な聖職者であればあるほど言葉をよく吟味して、文章においても微に入り細をうがつ配慮が必要であると思う。そして何よりも、読者に対して真実だけを伝えることである。この様に小さなことに忠実でなければ、伝道への扉は大きく開かれないであろう。
次に余談として述べたいことは、漱石の精神障害が分裂病であれ躁鬱病であるにせよ、後に、梅毒性の疾患と係りを持つことになる。その感染源は約二年間に及ぶロンドン留学時代に遡る。この頃が漱石の生涯で、二回目の精神異常の時期にあたる。往時、「漱石ロンドンで発狂」のニュースが日本まで届いていた。
日本の病跡学(パトグラフィ)界が、どこまで漱石と梅毒における因果原理を認めているかは知る由もないが、今から二十五年程前に、私は元大阪警察病院の精神科、医長の互恵を受けて、膨大な論文の閲覧に成就したことがある。それから数年の歳月を経て、私は漱石の梅毒と神経衰弱の関連における信憑性を説いたエッセイを、日本の経済新聞に連載し始めた。すると多方面から数多の反響があったのである。
「智に働けば角が立つ、上に掉(さお)させば流される。意地を通せば窮屈(きゅうくつ)だ。とかくこの世は住みにくい」(夏目漱石/『草枕』より)
夏目漱石が託つと、何と雄渾(ゆうこん)な文学へと変貌を遂げるのだろうか。傑出人と狂気、それは漱石が文豪として君臨するための必須の条件であったに違いない。
登録:
投稿 (Atom)